現在位置:トップページ > 市政情報 > 施策・計画 > 公共施設マネジメント > 計画・構想 > 公共施設マネジメント基本方針
ページID:5038
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
公共施設マネジメント基本方針
富士市公共施設マネジメント基本方針とは
富士市では、平成22年4月に策定した「第2次富士市行政経営プラン」の中で、「将来世代に過度の負担を残さない財政運営の実現」を図るため、「公共施設マネジメントの推進」を打ち出し、平成26年3月には、公共建築物の現状を把握する白書としての位置付けを持つ「富士市公共建築物保全計画」を策定するなど取組を進めてきました。
一方で、国は、「インフラの老朽化が急速に進展する中、『新しく造ること』から『賢く使うこと』への重点化が課題である。」という認識のもと、平成25年11月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定しました。地方においては、こうした国の動きと歩調をあわせ、行動計画及び個別施設計画の策定が要請されています。
本基本方針は、本市における公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための基本的な指針として位置付けるとともに、地方における行動計画である「公共施設等総合管理計画」に相当するものとしても位置付けます。
対象範囲
本基本方針の対象とする公共施設は、「公共建築物(ハコモノ)」と「土木系インフラ」、「その他公共施設」の3つに区分するものとします。
「公共建築物(ハコモノ)」については、別途計画を有する市営住宅、プラント施設及び企業会計である病院(以下「市営住宅等」という。)とそれ以外の建築物を区別して検討を行うこととし、市営住宅等以外の建築物を本基本方針では「一般公共建築物」と呼称します。
また、土地は公共施設ではありませんが、資産として適切に管理を行うため、対象に加えるものとします。
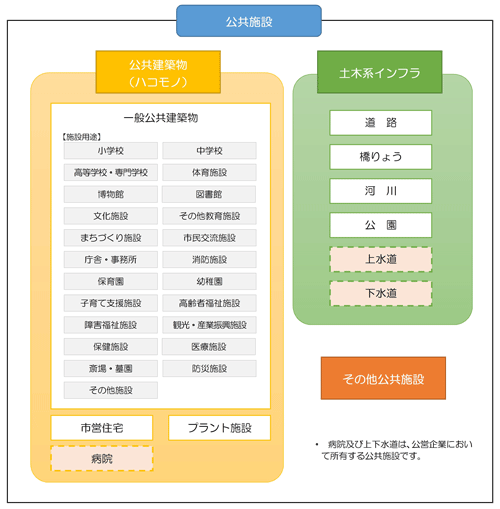
図1 公共施設マネジメント基本方針の対象範囲
公共施設の状況
1 公共建築物
| 施設分類 | 建物数 | 棟数 | 延床面積(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 一般公共建築物 | 226 | 448 | 579,059 |
| 市営住宅 | 26 | 116 | 128,427 |
| プラント施設 | 3 | 8 | 14,636 |
| 合計 | 255 | 572 | 722,122 |
一般公共建築物の延床面積は、約58万平方メートルです。このうち、建築後30年以上を経過した建築物が47%、15年以上30年未満の建築物が36%と非常に多くあるため、老朽化による安全性の問題に加えて、改修工事費が増大していくことが懸念されます。そのため、人口動向と財政状況と合わせて、必要な施設とサービスの量を把握するとともに、管理運営の効率化や計画的な維持管理の仕組みによるコスト縮減が重要になります。また、時代のニーズを見据えたサービスの提供と施設のあり方の検討も必要となります。
市営住宅は、昭和40年代後半に大量供給されたストックが更新時期を迎える中、早期の建替や、計画的な修繕・改善により長寿命化を図るなど、効率的・効果的な事業計画に基づくストック管理が求められます。また、居住者の高齢化や市民のライフスタイルも変化していることから、居住ニーズに対応した住環境の整備を検討していくことも求められています。
プラント施設のうちごみ処理施設は、現在、新環境クリーンセンターの建設計画が進められており、新施設の完成までは既存施設を適正に管理していくことが必要となります。また、生活排水処理施設は、従来から点検基準や法定点検に則り、点検を実施していますが、各種槽内の腐食や計装設備・電気設備等の各種設備の老朽化、管路施設の取付桝や取付管の破損が見受けられます。
2 土木系インフラ
| 施設分類 | 項目 | 数量 |
|---|---|---|
| 道路 | 延長 | 1,264,987メートル |
| 橋りょう | 橋りょう数 | 979橋 |
| 河川 | 延長 | 205キロメートル |
| 公園 | 公園数 | 394箇所 |
道路は、従来から幹線道路を中心とした補修及び改良事業を実施しているものの、高度成長期に建設された路線の老朽化が進行していることから、今後の維持管理費用の増加が懸念されます。道路施設の点検に関する動向については、中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故を契機として、国土交通省により舗装や道路附属物の点検要領が公表されるとともに、道路法の改正により横断歩道橋については、定期点検の確実な実施が義務付けられました。本市においてもこれらの対応として、定期的に点検を実施し、施設の損傷の見逃しを防止する必要がある一方で、点検費用の更なる増加が懸念されます。
橋りょうは、道路法の改正により、必要な知識及び技能を有する者による近接目視点検を5年に1回の頻度で実施することが基本とされ、従来と比較して点検費用が増加するものと見込まれます。その点検結果の評価についても、橋りょうの構成部材や損傷要因は多岐にわたっており、対策の必要性の判断が困難なことも想定されます。
河川は、水門や排水機場等の施設の老朽化が進行しています。また、近年の突発的かつ局所的な集中豪雨の増加により、河川管理施設の確実な機能維持が求められています。
公園の遊具については、長寿命化計画を策定し、計画的に修繕・更新を実施しているものの、依然として維持管理費用は不足しています。建物等についても点検やパトロールにより異常箇所の早期発見に努めているものの、老朽化対策の実施は不十分な状況です。また、建設当時と公園に対する市民のニーズも変化しており、統廃合により維持管理の効率化を図る必要があります。
3 公営企業が保有する公共施設
| 施設分類 | 項目 | 数量 |
|---|---|---|
| 病院 | 延床面積 | 35,182平方メートル |
| 上水道 | 導送配水管延長 | 1,231,815メートル |
| 下水道 | 下水管延長 | 831,712メートル |
病院は、24時間365日使用している特殊な利用形態であるため、大規模な改修を実施できず、施設及び設備の劣化が進んでいます。人命を預かる施設のため、早急に新規整備を含めた更新計画を検討する必要があります。
上水道は、高度成長期に建設された管路を中心に老朽化による維持管理費用の増加が懸念されます。これまで、高耐久性材料の管路の採用や計画的な施設の更新等を実施してきましたが、予算の制約もあり、更新事業の進捗率はなかなか上昇しない状況です。一方で、水需要の変化や耐震対策の必要性など、従来とは上水道事業に対する社会的要請も変化しており、これらへの対応が必要になってきます。
下水道の管路は、従来から計画的な点検や修繕・改築を実施していますが、管路延長は長く、点検費用等の財源の確保や人員の確保が課題となっています。処理場施設は、設備機器の更新に係る長寿命化を図っていますが、躯体の長寿命化等の必要性が生じてきます。一方で、管路及び処理場施設の維持管理に加え、地震災害発生に備えて下水道機能を確保できるよう、耐震対策にも取組んでいますが、耐震性の求められる管路延長が長く、処理場施設にも、耐震対策が必要になることから、それらの財源の確保も課題になっています。
公共施設の更新費用及び更新に向けた考え方
富士市が保有する公共施設を更新するための費用の推計は、年間平均で約155億円と見込まれます。
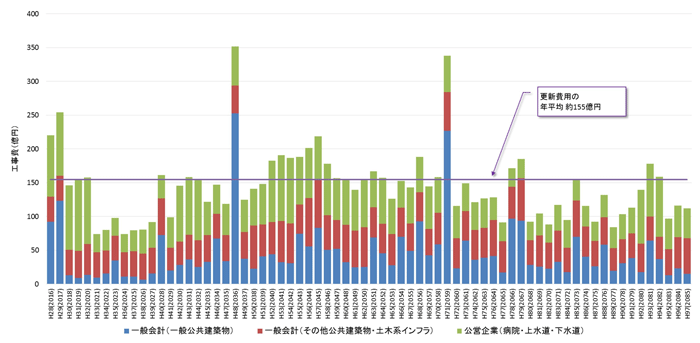
図2 公共施設の更新に係る将来の総費用推計
このうち、プラント施設にあっては、更新時に短期間で巨額の費用が発生するものであり、直近数年間の更新費用と比較することはできません。また、公営企業にあっては、独立採算制が原則とされており、更新費用の不足額に対しては、経営改善や料金収入の見直しを図ることで対応していくことになります。そのため、一般公共建築物、市営住宅及び土木系インフラのみ推定年間更新費用と過去5年間の平均更新費用の比較を次に示します。
| 項目 | 推定年間更新費用 | 過去5年間の平均更新費用 | 更新費の不足額 |
|---|---|---|---|
| 一般公共建築物 | 47億円 | 31億円 | 16億円 |
| 市営住宅 | 8億円 | 2億円 | 6億円 |
| 道路 | 18億円 | 13億円 | 5億円 |
| 橋りょう | 6億円 | 3億円 | 3億円 |
| 河川 | 7億円 | 7億円 | 0億円 |
| 公園 | 1億円 | 1億円 | 0億円 |
| 合計 | 87億円 | 57億円 | 30億円 |
比較の結果、過去5年間の平均更新費用に対する推定年間更新費用の不足額は、30億円にものぼることがわかりました。
なお、過去5年間の平均更新費用に、公共施設の新規整備に係る費用も含めると、年間約89億円になり、推定年間更新費用はこれにほぼ相当する額になります。道路の建設など、新規公共施設の整備はこれからも一定の必要性がありますが、この試算によると、公共施設の更新をすべて実施していった場合、新規整備のために費用を充てることができないことになります。
そのため、今後は既存施設の廃止も含めた抜本的な取組により、更新費用を抑制していくことが必要になります。
公共施設マネジメント基本方針
1 一般公共建築物に係る基本原則及び推進方策
原則1 公共サービスの提供方法を見直し、保有建築物の総量を削減します。
既存の一般公共建築物を更新する場合などには、当該建築物における公共サービスの提供方法について周辺施設や類似施設も含めて多角的に検討を行い、必要な機能やサービスを集約するなどの手法により建築物の総量を段階的に削減していきます。
また、新たな公共サービスの提供を行う場合は、そのサービスの必要性を十分検証するとともに、民間施設を含め、既存建築物の有効活用による公共サービスの提供方法を検討するものとし、新規建築物は原則として建設しません。なお、政策的な判断等により新規建築物の建設を行う場合は、他の建築物を計画的に廃止するなど総量の増加を防ぎます。
- 方策1-1 将来的なニーズを的確に把握し、建築物の総量の適正化を図ります。
- 方策1-2 民間で提供可能なサービスは民間に委ねます。
- 方策1-3 市単独での施設整備から広域的な施設利用に転換します。
原則2 一般公共建築物の維持管理手法を最適化し、ライフサイクルコストを縮減します。
公共サービスを精査した上で、継続して活用していくべき一般公共建築物については、長寿命化、予防保全の導入等により一般公共建築物の更新・修繕費用の軽減化、平準化を図るとともに、民間活力を積極的に導入することで施設の維持管理費用の縮減を図ります。
- 方策2-1 一般公共建築物の長寿命化を推進します。
- 方策2-2 一般公共建築物の計画的な保全体制を整備します。
- 方策2-3 民間活力の導入により一般公共建築物の更新費用及び維持管理費用を縮減します。
原則3 一般公共建築物の資産価値を最大限引き出すために、効果的に利活用していきます。
これまで多くの一般公共建築物は、原則として一つの機能に対して一つの施設という考えに基づき整備されてきました。今後、人口が減少し、財政規模が縮小していく中で一般公共建築物の保有量は削減せざるを得ませんが、これまでの施設整備の考え方を転換し、一つの施設に複数の公共サービスを集約するなどにより、市民の利便性を向上させるとともに、市民が集う魅力ある施設を形成します。また、一般公共建築物は市民共通の財産であることを強く認識し、最大限効果的な運用を行います。
- 方策3-1 施設の潜在的な魅力を引き出せるよう、最大限有効活用を図ります。
- 方策3-2 一般公共建築物を資産として捉え、効果的な運用により収益を生み出します。
2 土木系インフラに係る基本原則
原則1 投資コストを平準化します。
更新時期の集中を軽減するため、施設の劣化状況や利用状況などにより事業の優先度を判断し、計画的な維持管理、予防保全による長寿命化を行い、土木系インフラの投資コストを平準化します。
原則2 維持管理手法や整備手法を見直します。
予防保全型による維持管理手法の導入を進めながら、施設の性質等に応じて事後保全型及び観察保全型による維持管理手法と使い分けることで効果的な維持管理を行うとともに、最新技術を活用した維持管理を行うことで維持管理コストを縮減します。
さらに、コンパクトシティの考え方の下、将来的な人口減少に合わせ、施設の統合、廃止及び縮小など選択と集中による効果的な整備手法に転換していくことで適切に整備コストを縮減します。
3 目標の設定
公共施設のうち、土木系インフラについては数量の削減は困難であることから、過去5年間の平均更新費用と推定年間更新費用の差を念頭におきながら、長寿命化(予防保全)による更新費用のコスト縮減、高耐久性の材料や新工法を採用したライフサイクルコスト縮減、包括委託(PPPなど)による維持管理コスト縮減などを積極的に行い、現在の投資額保持に努めます。
また、市営住宅や公営企業が保有する公共施設については、将来的な更新費を念頭におきながら、個別に計画を策定し、更新費用の縮減に努めていきます。
そして、一般公共建築物については、将来的な更新費用を現在の水準に抑えるために必要な削減量を算出した結果、次のとおり削減目標を設定します。
目標:一般公共建築物の延床面積20%削減
公共施設マネジメント基本方針をパンフレットを作成しました

公共施設マネジメント基本方針をわかりやすく説明したパンフレットを作成しました。4コママンガを活用し、親しみやすい内容になっていますので、ぜひご覧ください。
富士市公共施設マネジメント基本方針パンフレットのダウンロード(PDF:6,715KB)