現在位置:トップページ > 市政情報 > 施策・計画 > 公共施設マネジメント > 計画・構想 > 公共施設マネジメント市民ワークショップ
ページID:5036
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
公共施設マネジメント市民ワークショップ
平成26年度公共施設マネジメント市民ワークショップ



市民ワークショップ開催概要
- 富士市の公共施設の現状と課題について、市民の皆さんと認識を共有するため
- 公共施設が提供しているサービスについて、利用者の視点で考えるため
- これからの公共施設のあり方について、市民の皆さんと一緒に考えるため
公共施設マネジメント市民ワークショップを平成26年10月18日及び25日の二日間にわたり開催しました。
参加者について
富士市在住の18歳以上の市民の方(平成26年7月1日現在)から1,000人を無作為で抽出し、そのうち、参加申込みをいただいた方及び富士市立高校、静岡大学、常葉大学の学生の計36人(うち2人は当日欠席)が参加しました。
ワークショップの概要
参加者の皆さまには、4つのグループに分かれていただき、グループワークを行いました。今回は、公共施設で行っている「サービス」に着目し、次のとおり検討を進めていきました。
- Aグループ:一般市民(9人)
- Bグループ:一般市民+高校生(9人)
- Cグループ:大学生+高校生(9人)
- Dグループ:大学生+高校生(9人)
1 サービスの使い方を考えよう
富士市にはさまざまな公共施設があります。これらは、それぞれ目的を持って建てられたものであり、目的に応じて行政側の視点から、そこで行っているサービスがあります。これに対して利用者である市民の視点から、その施設では、「どんな人が」「何をする」か、また、「どのように使う」かを考えてもらいました。
| 施設名 | サービス(行政の視点) | サービス(利用者の視点) |
|---|---|---|
| 地区まちづくりセンター | 各種証明書の発行 | 市民が住民票などを受け取る |
| 地区まちづくりセンター | 会議室の提供 | 町内会の役員が話し合いをする |
| 体育館 | 屋内運動場の提供 | 市民がスポーツの練習をする。 |
2 サービスを提供する場所を考えよう
次に、各グループで利用者の視点から出されたサービスが、次の4つの範囲のうち、どの範囲で行われるべきか考えてもらいました。
- 自分が住んでいる地域(小学校区)
- 隣の地域(中学校区程度)
- 市全体
- 他市、隣の市
3 公共サービスの必要性を考えよう
公共施設で提供されているサービスには、民間で類似のサービスが行われているものもあります。そこで、各グループから出されたサービスを公共が行うべきか、民間が行うべきか考えてもらいました。
4 必要なサービスの優先順位を考えよう
市の財政状況が悪化している中で、現在提供されている全てのサービスが今後も継続していけるとは限りません。そこで、各グループから出されたサービスについて、何を優先的に行っていくべきか順位付けしてもらいました。
5 サービスの提供方法を考えよう
1~4までの検討をもとに、各サービスについて、次のような考え方により、どのようなあり方が望ましいか考えました。
- サービスを集める
- (提供範囲で集める)同じ範囲で提供されるべきサービスは、同一の施設で提供できる可能性があるので、実現可能と考えられるものについてサービスをまとめる。
- (サービスの性質で集める)提供範囲は異なっていても、類似のサービスであって、より近い範囲にサービスをまとめることで利便性が向上するもの、又はより遠い範囲にサービスをまとめても差し支えないものについてサービスをまとめる。
- サービスをやめる
- (廃止する)同じサービスが多いものは、どこかの施設にサービスを集約し、サービスの数を減らす。
- (民間に移譲する)民間で提供できるサービスは、民間に移譲し、サービスの数を減らす。
市民ワークショップの結果概要
グループごとの検討結果の傾向
一般市民のグループと学生グループの検討結果を比較すると、それぞれのサービスの提供場所、必要性ともにほぼ共通の結果が得られました。
ただし、一般市民が入っているグループの方が、「施設配置は広域でよい」「民間に移管してよい」というサービスが多い傾向が見られました。これは、一般市民の方が「車による移動が可能であり行動範囲が広いこと」、「社会経験から民間による類似サービスがイメージしやすいこと」などの理由が考えられます。
意見の総括
1 サービスの提供範囲
利用頻度が高いサービス、アクセスのしやすさや安全面から利用者が主に子どもや高齢者のサービスなどは近隣にあるべき、スケールメリットが生かせるサービス、利用者層が広範なサービスなどは広域でよいという結果が見られました。
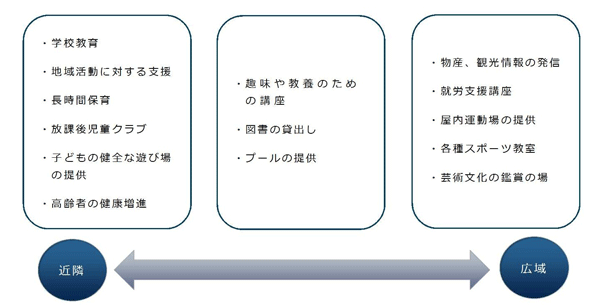
2 サービスの必要性
民間の方が充実したサービスが受けられるもの、市場原理が働くものなどは、民間でもよいという意見が多く出ました。
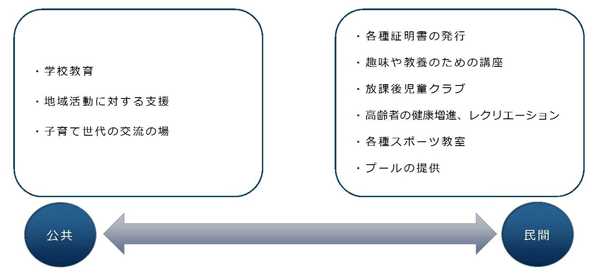
3 サービスの提供方法
次のようなサービスについては、統合できるのではないかという意見が出ました。
- 利用者や利用目的が同一のサービス
- 高齢者向けのサービス(高齢者の余暇活動、教養講座など)
- 子育てサービス(保育、児童クラブ、子どもの遊び場など)
- 複数の施設で重複しているサービス
- 趣味、教養、スポーツなどの講座
- 会議室、集会所、ホールなどの場の提供
- 異なるサービスを1箇所で行うことで施設の有効活用が図れるもの
- 各種証明書の発行、図書の貸出し、必要な資料提供(利用者の利便性の向上を図る)
- 高齢者の交流の場、子育て世代の交流の場、スポーツ教室、各種講座(利用世代や専門性で分けないことでにぎわいを生み出す)
- 観光施設、集会施設、イベント会場(スケールメリットを生み出す)
このようなサービス提供案により、いずれのグループも施設量は減らせるという結果となりました。
ワークショップ終了後のアンケート結果の概要
1 市民ワークショップへの参加動機を教えてください。
| 以前から公共施設に 関心があった |
今回の件で公共施設に 関する問題に興味を もった |
市政に関与したかった | その他 |
|---|---|---|---|
| 5.9% | 32.4% | 20.6% | 41.2% |
2 公共施設マネジメントの取り組みは、理解できましたか。
| よく理解できた | 少し理解できた | 少し難しかった | 理解できなかった |
|---|---|---|---|
| 39.4% | 51.5% | 9.1% | 0% |
- ワークショップに参加したことで、現在の公共施設の状態について知ることができた。
- 施設のランニングコストが分かりづらかった。例えば、インパクトのある大きな施設だけでも説明があった方がよかったと思う。
3 市民ワークショップの内容は、理解できましたか。
| よく理解できた | 少し理解できた | 少し難しかった | 理解できなかった |
|---|---|---|---|
| 54.5% | 42.4% | 3.0% | 0% |
- 紙に付箋紙を貼りながら、具体的に考えていけたから。
- 1ステップずつ議論することで理解しやすかった。
- 難しかったが、話し合いをしているうちに理解ができた。
4 今回参加して、公共施設について意識が変化しましたか。
| 関心が深まった | 少し関心をもった | 変わらない | あまり関心はない |
|---|---|---|---|
| 42.4% | 42.4% | 6.1% | 0% |
- 様々な類似したサービスが複数の施設で行われていることから、その施設の必要性やサービスに対するコストなどを考えることができた。
- 今回、公共施設を何のためにどう使うのか考えることができてよかったです。
- 公共施設のみに焦点を当てるべきではないと思います。人口の増加や税収面等の課題にも触れてみたいです。
5 市民ワークショップへ参加して良かったですか。
| とても良かった | やや良かった | あまり良くなかった | 良くなかった |
|---|---|---|---|
| 66.7% | 33.3% | 0% | 0% |
- 一般の方の班と学生だけの班でまとめた結果に違いがあったのが面白かったです。
- いろいろな価値観を共有できたため。
- 私たちの意見が今後どのように反映されていくのかが不明。
6 その他、ご意見・ご質問等をご記入ください。
- 市民の声を聞くのはいいが、それを言い訳にするような判断にならないように市政を進めてほしい。
- 他の問題(公共交通、上下水道)でもやってほしい。
- 若い世代が参加していたため、新鮮でした。
- もっと大勢の参加を希望する。