ページID:281
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
国民保護計画について
国民保護計画の概要について説明します。
国民保護とは
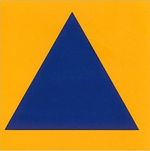
近年の国際情勢を見ますと、2001年の米国同時多発テロ、2004年のスペイン同時多発列車爆破テロ事件、2022年のロシア・ウクライナ戦争など、世界各地で戦争やテロなどが起きており、日本でも、いつこのようなことがおきてもおかしくない時代になってきています。国民保護とは、万が一、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、迅速に住民の避難を行うなど、国、県、市、関係機関などが協力して、市民の生命、身体、財産を守り、攻撃等による被害を最小化するための事前の備えや仕組みのことです
左のマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。このマークは、ジュネーヴ諸条約追加議定書に規定されており、民間防衛団体、その要員、建物および物品の保護ならびに避難所を識別するためのものです。
国民保護協議会とは
国民保護協議会とは、国民保護法第39条の規定に基づき、設置されるものです。協議会を設置する目的は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議することおよび、重要事項に関し、市長に意見を述べることです。また、市長は、国民の保護に関する計画を作成、または変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとされております。
武力攻撃事態の想定
武力攻撃事態の想定は、武力攻撃の手段、その規模の大小、攻撃パターンなどにより異なることから、どのようなものとなるかについて一概にはいえませんが、国民の保護に関する基本指針において、以下の4つの類型を想定し、国民の保護のための措置の実施にあたって留意すべき事項を明らかにしています。
- 着上陸侵攻
- 弾道ミサイル攻撃
- ゲリラ・特殊部隊による攻撃
- 航空攻撃
緊急対処事態とは
武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要な事態をいいます。なお、緊急対処事態は、後日、武力攻撃事態であると認定される事態を含んでいます。
国民保護のための情報伝達手段
国は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があるときは、警報を発令し、直ちに都道府県知事等に通知します。また、住民の避難が必要なときは都道府県知事に対し、住民の避難措置を講ずるよう指示します。これを受け、都道府県知事は、警報の通知や避難の指示を行い、市町村の住民広報を通じて住民に情報が伝達されます。武力攻撃事態等においては、このような情報が迅速かつ確実に伝達されることが大変重要となります。このため、国民保護のための情報伝達の手段については、防災無線、衛星通信など複数の経路を確保することとしています。また、国民保護における市の主な役割は、「警報の伝達」「避難指示の伝達」「避難住民の誘導」などです。警報の伝達については、国で定めたサイレン音や、テレビ・ラジオ等により市民の皆様に伝達します。