現在位置:富士の魅力トップページ > 頼朝と曽我兄弟~源平合戦前後の富士地域~ > 鎌倉殿へのはじまり > ある担当者のつぶやき【3月放送分】第9回~第12回
ページID:7492
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
ある担当者のつぶやき【3月放送分】第9回~第12回
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放送が開始されています。
学生時代は日本史が苦手だった担当者が、大河ドラマの感想をつぶやいたり、物語をより深く楽しむためのポイントを頑張って解説したりします。
第十二回「亀の前事件」(2022年3月27日放送):更新日3月31日

坂東武士たちが御家人として源頼朝に仕えるようになったとはいえ、クセの強い彼らをまとめ上げるのは一苦労のようです。源義経は自分を特別扱いしてほしいようですが、頼朝はあくまで御家人の一人として扱っています。誰か一人を贔屓することは、他の者たちから不満が出ることが分かっているのでしょう。こんな時、義経を諫めるのが北条義時の役目なのでしょうが…今のところ、やることの全てが裏目に出てしまっています。
家族の絆の強い北条家による圧迫面談、中々の迫力でしたね。流石の頼朝もタジタジでした。当事者の亀といえば、次のターゲットをロックオン。これで平和になるかしら…と思ったら、再び八重が戻ってきそう。八重さん、一途すぎます。政子の怒りはまだ収まりそうにありませんね。
ポイント解説
政子が行った「うわなり打ち」とは?
うわなり打ちの発祥については不明ですが、平安時代の中頃には存在していたことが史料により確認されています。妻が夫の愛人もしくは後妻の家を襲撃する、この風習は時代とともに明確にルール化され、江戸時代まで続きます。
平安時代には相手の命を奪うこともあった過激なうわなり打ちですが、そのうちに襲撃日と武器(箒やしゃもじ等)を事前通告し、相手の命は狙わないという作法が生まれ、儀式化していったそうです。
亀へのうわなり打ちは、政子の嫉妬深さを表すエピソードとして有名ですが、平安時代には珍しくない行為だったようです。
また、貴族であり、跡継ぎを生むための妾の存在が通常であった源頼朝とは違い、政子の出身である関東の武士たちは、もともと農業を営む村であり、男女共に働き、対等な関係であったため、一夫一妻が通常でした。政子にとっては、頼朝の行動はひどい裏切りに感じたのかもしれません。
他にも、跡継ぎを生むのに苦労している政子は、頼朝の愛人は自分の立場を危うくする危険な存在と感じていた、という説もあるそうです。
第十一回「許されざる嘘」(2022年3月20日放送):更新日3月25日

北条義時、見事に玉砕です。男泣きする姿に同情しますが、あんなに八重にそっけなくされていたのに、上手くいくと思っていたことが不思議です。八重へのプレゼントも喜ばれていると勘違いしていましたし、義時には思い込みが強いところがありますね。
八重と伊東祐親の穏やかな親子のひとときは、祐親の結末を知っていると、何とも言えない切ないシーンです。祐親と八重が和解する時間を作れたこと、義時がした祐親の命乞いは無駄ではなかったのだと思います。義時の優しさ、八重に伝わると良いですね。
源頼朝と義経の、それぞれの冷ややかな表情が印象的でした。自分の目的のためには犠牲を厭わないところが似ています。初めて頼朝に反抗した義時は、これからどうなるのでしょうか。
頭の切れる梶原景時と、暗殺を得意とする善児が手を組むなんて、最も恐ろしいタッグが生まれてしまいました…景時は善児を雇って何をさせるつもりなのか、気になります。
ポイント解説
鎌倉幕府ができたのはいつ?
私が学生の時は、鎌倉幕府の誕生は1192年と学びましたが、現在の歴史の教科書では、1185年とされています。鎌倉幕府の成立日は、「幕府とは何か?」をどう捉えるかによって変わってしまうため、研究者の間でもずっと議論されているそうです。
鎌倉幕府の成立について、近年の主流な説は、次のA~Fの6つあります。
- A 1180(治承4)年:頼朝が鎌倉に入る
- B 1183(寿永2)年:頼朝が東国支配権を朝廷から事実上の承認を受ける
- C 1184(元暦元)年:鎌倉に公文所・問注所(財政・裁判機関)を設置
- D 1185(文治元)年:頼朝が守護・地頭を任命する権利を獲得
- E 1190(建久元)年:頼朝が右近衛大将に任命される
- F 1192(建久3)年:頼朝が征夷大将軍に任命される
幕府とは、武士による武士のための政治組織のことを言いますが、Aの説は頼朝と武士たちに主従関係が生まれ、頼朝が「鎌倉殿」となった年を指しています。B~Dの説は政権のシステムが成立する過程を重要視しています。E、Fの説は、官位という形式的な面を重要視しています。
現在支持されているDの説では、守護(治安維持のための軍事・警察権を行使する者)・地頭(土地の管理や年貢の徴収する者)の任命権を獲得することで、頼朝が武士を支配する責任者となったことを重要視しています。
鎌倉幕府が一日で誕生したのではなく、時間をかけて出来上がっていったことを考えると、将来、また成立日が変わるかもしれませんね。
第十回「根拠なき自信」(2022年3月13日放送):更新日3月18日

源頼朝と坂東武士たちの心の距離がなかなか縮まりません。今は、お互いに利害が一致していて協力関係にありますが、平家追討という目的が達成された後はどうなってしまうのでしょうか。このままでは、頼朝と坂東武士たちで対立してしまいそうです。大庭景親の最後の言葉が予言のようで、ぞっとします。
八重が近くにいて、北条義時はだいぶ浮かれていますね。八重は人の好意に鈍感なのではなく、義時たちを相手にしていないようです。三浦義村のトレンディドラマばりのクールな口説き文句もばっさり切られてしまい、笑ってしまいました。
そんな八重に、頼朝と親密な仲であることをみせつける亀、なんて大胆な人…。今後も、ハラハラする展開が続きそうです。
ポイント解説
源義経の伝説について
初めての戦で自信満々だったり、手柄を立てられず癇癪を起こしたり…ドラマの源義経は、とても印象の強いキャラクターです。
実際の源義経については、史実と伝説が入り交じり、わからないことが多いようです。きっと、たくさんの伝説が生まれるほど魅力的な人物だったのではないでしょうか。義経の有名な伝説を2つご紹介します。ドラマの義経をみていると、この伝説も本当かも…と思ってしまいます。
- 義経は天狗の修行を受けた?
父である源義朝が敗死し、鞍馬寺に預けられた義経はある日、僧とともに花見に出かけます。そこに見知らぬ山伏(やまぶし)が訪れると、山伏を気味悪がった一行は、義経を残して帰ってしまいます。ただ一人残された義経の素性を知り憐れんだ山伏は、自分の正体は大天狗であると明かし、平家討伐を達せられるよう兵法の秘伝を授けたのです。
- 義経と弁慶の出会い
乱暴者だった弁慶は、お寺に預けられますが、まじめに修行しないため、お寺を追い出されてしまいます。その後も悪行を繰り返していた弁慶は、そのうち、京で千本の刀を集めるという誓いを立てて、道で遭遇した人を襲ったり、武士と決闘したりして999本まで刀を集めます。
あと一本と獲物を探していた弁慶は、五条大橋で笛を吹いている義経と出会います。義経の立派な刀に目をつけた弁慶は挑みかかりますが、義経の見事な身のこなしに敵わず、敗北してしまいます。それ以来、弁慶は義経の家来として付き従うようになりました。
第九回「決戦前夜」(2022年3月6日放送):更新日3月10日
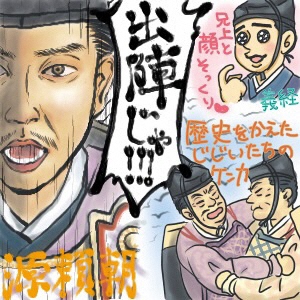
富士川の合戦についてご存じの方も、まさかの展開に驚いたのではないでしょうか。じじいたちのケンカが歴史を変えることになるとは…思いもよらぬストーリーで面白かったですね。息子の宗時が亡くなってから北条時政の元気がなくて心配ですが、おちゃめな姿が戻ってくるのを楽しみにしています。
ヒーローのように八重を救出した義時ですが、八重に気持ちは通じていないようです。八重が人の好意に鈍いのか、もしくは義時に興味がないのか。夫の最期のときは、八重が彼を大切に思う気持ちが垣間見えましたが、そのあと、源頼朝の傍にいたいと義時にお願いしていますし、八重の頼朝を思う気持ちはまだまだ強いようです。
政子、八重、亀が頼朝の近くで暮らすことになりました。なにやら一波乱ありそうです。
ポイント解説
どうして頼朝たちは京都に行かなかったの?
ドラマでは頼朝は勢いに乗って京都へ向かい、平氏を討とうとしましたが、三浦義澄たちは兵糧が尽きることを理由に拒みました。
兵糧とは、戦での兵士たちのご飯のことです。当時の武士たちは、従軍する際、自分たちの武器や馬、ご飯など、必要なものは自力で用意するのが基本でした。兵糧が乏しくなると兵の士気が下がるため、重要なことだったそうです。
ちなみに、富士市原田にある飯森浅間神社は、富士川の合戦のとき頼朝軍が兵糧を置きそれを兵が守ったことから「飯守」と呼ばれ、現在の名前に変化したという言い伝えがあります。
また、兵糧の他にも、まだ頼朝に従っていない者たちの動きを危険視していたといわれています。京都へ向かう途中に背後から攻撃されるのを恐れ、いったん鎌倉に帰り、東国の統一、特に河内源氏たちを従わせることを優先しました。

