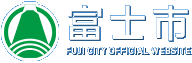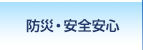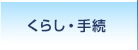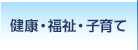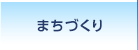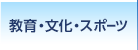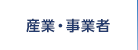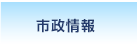富士のお茶振興・富士の茶娘について
2024年04月01日掲載
富士のお茶について
富士のお茶の歴史
明治初め、茶業における先覚者の一人であった野村一郎は、富士愛鷹両山の間の原野を開墾し、茶園を造成したとされています。 その後、製茶技術の向上のため近江から製茶師を招き、自らも研究を重ねて野村式製茶法を完成させました。
当時、茶は重要な輸出品でしたが、野村一郎の茶は、イギリスや清(中国)の茶商人から「天下一品」の折り紙をつけられました。 その製茶技術はこの地域に広がり、現在のような茶の一大産地へと展開されています。
富士のやぶ北茶・農林水産大臣賞受賞
明治の中頃、静岡のある藪の北側の茶園から珍しい茶の木が発見されました。その後、この茶の木をもとに改良が繰り返され、苦心の末、優良な新品種「やぶ北」が誕生したのです。
この品種は戦後、富士山麓一帯の広大な土地で栽培されはじめ、これが奇跡的な大成功を収めました。 当地の地質はその生育に最も適し、農家の人々が真心こめて生産し、それが近代的な組織により集荷され、ここにはじめて発祥栽培の土地にちなんで「富士のやぶ北茶」と名づけて全国に送り出されるようになりました。
富士市の茶業者の努力により生み出される茶の逸出した香りと味は、一度飲まれた方に深い感銘を与え、農林水産大臣賞にも輝いております。
富士市茶手揉保存会について
富士市茶手揉保存会は、昭和57年2月に会員相互の技術の交流とその親睦を図り、手揉製茶技術の向上保存に務め、近代製茶法改善と併せてその芸術的技術及び製品を広く公開展示して消費者にも茶の認識啓発をし、もって富士の茶業振興に寄与することを目的として発足し、現在市内で行われるさまざまなイベントにおいて富士の手揉み茶の啓発活動を行っています。
富士の茶娘について
富士市では、特産物である「富士のお茶」の消費拡大を目的に、様々な事業に参加していただくPRサポーターとして「富士の茶娘」の選出を昭和61年度から行っています。初代茶娘の任期は1年間でしたが、平成5年度の8代目から2年任期となり、2年に1回「富士の茶娘クイーンコンテスト」を開催し、富士の茶娘クイーン1名と富士の茶娘6名を選任してきました。令和3年度の22代目からは、これまでよりも幅広く富士のお茶のPR活動に取り組んでいくため、店員を7名から10名程度へと増員するとともに、従来の公開コンテストによる選考方法から、非公開の書類審査及び面接による方法へと変更しました。令和7年度の24代目では10名の新しい茶娘が選ばれました。
市内外のイベントで富士のお茶を呈茶したり、ポータルサイト・インスタグラムで魅力を発信したり、様々なPR活動に取り組んでまいります。
第24代富士の茶娘
 第24代富士の茶娘任命式
第24代富士の茶娘任命式
- 石川 清香(いしかわ さやか)さん
- 板谷 瑞貴(いたや みずき)さん
- 木田 美早(きだ みさき)さん
- 塩田 圭(しおた けい)さん
- 鈴木 詠美子(すずき えみこ)さん
- 原 みゆき(はら みゆき)さん
- 藤田 恵子(ふじた けいこ)さん
- 本田 恵理奈(ほんだ えりな)さん
- 室伏 恵(むろふし めぐみ)さん
- 山本 真央(やまもと まお)さん
お問い合わせ
農政課 農業振興担当(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2781
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp